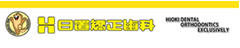

1期治療は、歯並びそのものを整えるのではなく、顎の骨の成長を正しく促して将来生えてくる永久歯のための土台を作る治療です。一般的に「歯科矯正=ワイヤー」というイメージがあるかもしれませんが、実際にはワイヤーを使った治療は少なく、将来に備えて土台を作ることが主な目的です。
取り外しができる装置(可撤式矯正装置)
取り外し可能な装置は、歯磨き時に外せるため、口内を清潔に保ちやすいというメリットがあります。ただし、24時間装着する必要がないため、効果が現れるまでに時間がかかることもあります。
床矯正(しょうきょうせい)・プレート
床矯正は、子供の成長に合わせて歯列の幅を少しずつ広げる治療です。歯の大きさに対して顎の骨が小さいことが歯並びの凸凹の原因である場合に用いられます。歯の裏側から装置を取り付け、装置内のネジで調整して段階的に歯が並ぶスペースを拡大していきます。永久歯が生えてからスペースを広げる場合は抜歯が必要になることもありますが、子供のうちに床矯正でスペースを作っておくと、抜歯が不要になることもあります。痛みが少なく、取り外し可能なため、歯磨きの際に支障がないというメリットがあります。ただし、咬み合わせが逆の場合など、床矯正のみで歯並びを整えるのが難しい場合もあります。また、症状によっては毎日半日以上の装着が必要な場合があり、装着時間を守ることが難しい子供もいるかもしれません。
バイオネーター(下顎の前方成長を促進させる装置)
バイオネーターは、下顎の成長が十分でなく、上顎が前に出てしまっている顎の咬み合わせを整える装置です。筋肉の動きを利用して下顎が前方に成長するように促します。装置はワイヤーとプラスチックで構成されており、ネジで装置の幅を調整できます。下顎の成長を促すことが主な目的ですが、横方向にも拡大が可能です。就寝中に装着するため、学校や食事の時間には外すことができ、微調整が可能なため痛みが少ないというメリットがあります。ただし、慣れるまでは違和感があり、就寝中に無意識のうちに外してしまうことがあるため、毎日決められた時間の装着が必要です。最初は睡眠時以外にも装着して慣らすなどの工夫が必要になるかもしれません。
ツインブロック
ツインブロックは、下顎が奥に引っ込んでいることで出っ歯になってしまった場合に使用されます。上下両方の顎に装着し、噛むと上下の装置が滑り台のように滑って下顎を正しい位置に誘導する仕組みです。バイオネーターは一体型の装置ですが、ツインブロックは上下が別々になっており、就寝中に外れにくい特徴があります。重い症状にも適しており、痛みが少なく取り外して歯磨きができるメリットがありますが、就寝中や食事中にも装着する必要があり、子供にとっての負担が小さくないデメリットもあります。
F.K.O(アクチバトール)
F.K.O(アクチバトール)は、下顎の成長が停滞しているために上顎が前に出てしまい、咬み合わせが深すぎたり、出っ歯になったりしている場合に使用されます。上下が一体になった装置を口の中に入れて、咬み合わせを正しい位置に誘導し、噛む機能を利用してズレを改善し、下顎の成長を促します。装着中は話しにくくなるデメリットがありますが、大きな装置の割に子供への負担が少なく、就寝中に装着するため日常生活にそれほど影響がないメリットがあります。
インビザライン・ファースト
インビザライン・ファーストは、歯型に合わせた透明なマウスピースを装着して歯並びを矯正する装置です。下顎を前方に成長させつつ、歯並びを少しずつ正しい位置に誘導していきます。約6〜10歳の間の乳歯が残っている時期から始めることができ、ワイヤー治療より痛みが少なく、透明なので装着していてもほとんど目立ちません。金属を使用しないため、金属アレルギーがある子供でも使用できるメリットがあります。ただし、1日の装着時間が20時間前後と長く、食事や歯磨き以外では常に装着している必要があり、子供によってはストレスに感じる可能性があります。また、6歳臼歯と前歯が2/3以上生えている必要があり、子供の骨格や顎の状態によっては適応外となることもあります。
トレーナーマウスピース
トレーナーマウスピースは、口周りの筋肉をトレーニングして、不正な咬み合わせの原因となっている舌の癖や口呼吸などを改善し、顎と歯列の正しい発育を促す装置です。トレーニングを続けることで舌や頬、唇などの筋肉のバランスを整え、歯と顎を正しい位置に誘導します。
取り外しができない装置(固定式矯正装置)
固定式の矯正装置は常時装着したままなので紛失の心配がありませんが、歯磨きをしても汚れが残りやすいため、磨き残しに注意が必要です。
リンガルアーチ(舌側弧線装置)
リンガルアーチは、主に2つの目的で使用されます。一つは、乳歯が抜けた後に生えてくる永久歯のスペースを確保するためです。乳歯が抜けた後の隙間に隣の歯が移動してしまう習性があり、永久歯が生えるスペースを確保することで、生え変わったときにきれいな歯列を作ることができます。もう一つは、上下の歯の咬み合わせが逆になっている反対咬合の治療です。この場合は前歯部にワイヤーを装着して軽い圧をかける使い方をします。永久歯のためのスペースを確保する目的で使用される場合は、奥歯を土台にしてワイヤーを歯の裏側に通すので、外見からは矯正中であることがわかりにくく、痛みもそれほど強くありません。しかし、装置を外すことができないため、装置が気になって指や舌で触って傷ついてしまったり、歯磨きをしても汚れが残りやすくなったりといったデメリットもあります。
固定式拡大装置(GMD・ペンデュラム・クワドヘリックス)
固定式拡大装置は、奥歯に器具を固定し、歯列を後方や側方に動かす装置です。歯の位置をずらすことでスペースができるので、抜歯をしなくても歯並びを矯正しやすくなります。器具のほとんどは歯の裏側に固定されるので大きく目立つことはありませんが、奥歯に装着する器具がやや見えることはあります。また、歯磨きが難しくなるため虫歯になるリスクが高まったり、食べ物が詰まりやすくなったりといったデメリットがあります。
急速拡大装置
急速拡大装置は、短期間で歯を動かす土台となるスペースを拡大する装置です。効果には個人差があるものの、1ヶ月もかからずにスペースを拡大できることもあります。上顎に装置をつけ、毎日ネジを回して徐々にスペースを拡大していきます。ネジを回す頻度は歯科医師の指示を確実に守る必要があり、自己判断で回転数を変えると、歯が抜けてしまうこともあるので注意が必要です。この装置が適応するのは、上顎骨が成長しきる9〜10歳ごろまでの、歯並びの乱れが大きなお子さまが抜歯をせずに矯正したい場合に限られます。また、スペースが拡大したあとも、元に戻らないように装置をしばらくつけておく必要があります。
タングガード
タングガードは、舌で前歯を押さないようにガードする、上顎につける柵のような装置です。話す時やつばを飲み込むときなどに舌を前に突き出す癖があるお子さまは、その習慣から上下の歯が咬み合わなくなったり、口が閉じにくくなったりしやすいので、その改善と防止に使われます。タングガードを装着すると同時に、舌や唇などの筋肉のトレーニングを並行して行うこともあります。
2?4(ツーバイフォー)や2?6(ツーバイシックス)
2?4や2?6は、部分的に前歯の歯並びを矯正する装置です。奥歯2本を土台にして、前歯4本(もしくは6本)にブラケットという小さなプレートを取り付けてからワイヤーを通します。前歯がまだ乳歯の場合は、前もって歯列を整えておくことで、生え変わった後の永久歯の歯列を整えることができます。また、反対咬合や上顎前突の矯正に使われることもあり、状態によってはヘッドギアやフェイスマスクなどを併用することもあります。歯の表側からワイヤー装置をつけるため、見た目が目立ちやすいデメリットがあります。